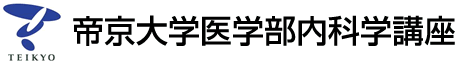研究成果
呼吸器・アレルギー学のメンバーからの論文報告を記載します。
帝京大学 呼吸器・アレルギー学 筆頭著者論文
Clinical Remission of Mild-to-Moderate Asthma: Rates, Contributing Factors, and Stability.
Ishizuka M, Sugimoto N, Kobayashi K, Takeshita Y, Imoto S, Koizumi Y, Togashi Y, Tanaka Y, Nagata M, Hattori S, Uehara Y, Suzuki Y, Toyota H, Ishii S, Nagase H.
J Allergy Clin Immunol Glob. 2025 Jan 30.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40091885/
(概要)
喘息では、治療下で完全に症状や増悪をコントロールできた状態を「臨床的寛解」として定義しています。しかし、その定義は世界的にみると、重症喘息を対象とする研究ばかりで、喘息の大多数を占める軽症から中等症での臨床的寛解の実態は不明でした。本論文は、この実態を明らかにした帝京大学における研究成果で、石塚が筆頭著者として報告しました。
本研究では、80%以上の軽症から中等症の喘息患者が臨床的寛解を達成しているものの、その評価によりunder treatmentを検出できる可能性を示しました。また、後ろ向きに臨床的寛解の安定性を評価し、軽症から中等症喘息では10年前の臨床的寛解達成例の90%程度が10年後もそれを維持していることから、新たな治療目標として妥当な可能性も示されました。この知見は、2024年10月に日本アレルギー学会からリリースされた、「喘息予防・管理ガイドライン2024」における臨床的寛解の定義にも反映されています。J Allergy Clin Immunol Globalは、米国アレルギー・喘息・免疫学会 (AAAAI)の公式雑誌のひとつで、2021年に創刊された若い雑誌です。わが国からも続々と興味深い報告が掲載されています。
(Abstract)
軽度から中等度の喘息の臨床的寛解:寛解率、寄与因子、安定性
- 背景
- 重症喘息の臨床的寛解(CR)については広く研究されているが、軽症から中等症喘息のCRについては未解明である。
- 目的
- 本研究の目的は、軽度から中等度の喘息患者におけるCR率、その要因、および安定性を明らかにすることである。
- 方法
- 喘息患者263例をレトロスペクティブに解析した。3成分CRは、増悪がないこと、経口コルチコステロイドを毎日服用していないこと、Asthma Control Testのスコアがウェルコントロールと同等であることと定義し、4成分CRは、これらのパラメータに加え、1秒間の強制呼気量が予測値80%以上であることと定義した。軽症から中等症および重症の喘息患者において、1年間のCRおよび10年間のCRの安定性がレトロスペクティブに解析された。
- 結果
- 軽症から中等症喘息患者のCR率は、重症喘息患者のCR率(4成分:33.9%、3成分:30.6%)と比較して有意に高かった(4成分:73.2%、3成分:81.0%)。喫煙指数が低いほど、3成分および4成分のCRに寄与した。肥満指数が低いほど3成分寛解に寄与し、発症が遅く喘息罹病期間が短いほど4成分寛解に寄与した。10年前に4成分寛解を経験した患者では、80.3%が寛解を維持し、3成分寛解を経験した患者では89.1%が寛解を維持した。10年後に4成分寛解が維持されなかった患者では、予測強制呼気量が減少したが、吸入コルチコステロイドおよび長時間作用性β-アゴニスト/長時間作用性ムスカリン拮抗薬の投与量に10年前と現在で差は認められなかった。現在のムスカリン拮抗薬の使用率は16.7%と低いままであった。
- 結論
- 強制呼気量の正常化を含むCRは、軽症から中等症の日本人喘息患者のほとんどにおいて獲得可能であり、持続可能である。これらの患者でCRを評価することは、過少治療を回避し、将来のリスクを軽減するのに役立つであろう。
Effectiveness of Mepolizumab in Japanese Asthma Patients with Diverse Backgrounds: Improvements in Rhinosinusitis Imaging (J-Real-Mepo).
Allergol Int. 2025 Jan 22.
Nagase H†, Kobayashi K†, Toma-Hirano M, Suzukawa M, Harada N, Masaki K, Miyata Y, Mayoko Tsuji M, Terada-Hirashima J, Komatsuzaki K, Sasano H, Mizumura K, Kagoya R, Shimizu Y, Yoshihara S, Kihara N, Miyazaki Y, Koya T, Sugihara N, Ishikawa N, Hojo M, Tagaya E, Tanaka A, Fukunaga K, Gon Y, J-Real-Mepo Investigators.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39848869/
(概要)
都内の大学病院を中心とした多施設共同研究で、重症喘息を対象とした生物学的製剤のリアルワールドでの効果や効果予測因子を検討したシリーズのひとつです。帝京大学が主幹となり、長瀬、小林がco-first authorとして、J-real-Mepo研究として報告しました (n=200)。メポリズマブ (IL-5抗体)の、患者背景や炎症背景によらない幅広い効果を示し、IL-5の好酸球活性化以外の機能が示唆される結果でした。また、当院耳鼻咽喉科の平野先生らと協力し、喘息に合併した副鼻腔炎の画像的改善もはじめて報告し、帝京アレルギーセンターとしても初めての報告となりました。本学から、iPOT-5試験に続いて発信された、2報目のIL-5抗体に関するリアルワールド研究成果です。
(Abstract)
多様な背景を持つ日本人喘息患者におけるメポリズマブの実臨床効果: 鼻副鼻腔炎画像の改善(J-Real-Mepo)
- 背景
- ランダム化比較試験(RCT)により喘息に対するメポリズマブの有効性が示されているが、特定の患者サブグループは除外されている。RCTと実臨床とのギャップを埋めるため、RCTから除外される可能性のある患者を含む多様な集団におけるメポリズマブの有効性を評価した。喘息を伴う慢性鼻副鼻腔炎(CRS)の画像所見および症状に対する効果も評価した。
- 方法
- 日本における患者を対象としたこのレトロスペクティブ観察研究(J-Real-Mepo:UMIN000045021)では、複数のエンドポイントを評価し、臨床背景と治療成績の関係を分析した。
- 結果
- メポリズマブは、年齢、肥満度、喫煙歴、合併症などの患者の特徴にかかわらず、増悪を有意に減少させ、喘息コントロールテスト(ACT)スコア、強制呼気1秒量を改善し、経口コルチコステロイド(OCS)投与量を減少させた。RCTの除外基準に関しては、29.4%の患者は増悪歴がなかった。これらの患者の25.4%が継続的なOCSを必要としたが、OCSの投与量は増悪歴のある患者と同様に減量された。喫煙歴が10箱年以上の患者における病勢コントロールとメポリズマブの有効性は、喫煙歴のない患者と同様であった。好酸球数が150/μL未満の患者では、好酸球増多の患者と比較してACTスコアが低く、OCSの使用量が多かったが、増悪とOCSの減少に関する有効性は同等であった。Lund-MackayスコアおよびCRS症状の有意な改善が認められた。
- 結論
- メポリズマブの有効性は、RCTの除外基準に該当し、疾患またはOCSの負荷が大きい患者を含む幅広い患者において証明された。これらの知見は、メポリズマブのRCTと実臨床試験との間で一貫した結果が得られていることを説明するものであろう。
ZFP36 family expression is suppressed by Th2 cells in asthma, leading to enhanced synthesis of inflammatory cytokines and cell surface molecules.
Cell Immunol. 2024 Sep-Oct:403-404.
Uehara Y, Suzukawa M, Horie M, Igarashi S, Minegishi M, Takada K, Saito A, Nagase H.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39067169/
(概要)
Th2細胞が発現するZFP36は、炎症抑制性に機能する分子であり、喘息ではその発現が減少していることを、上原が筆頭著者として、東京病院の鈴川先生との共同研究で報告しました。
(Abstract)
喘息ではTh2細胞によってZFP36ファミリーの発現が抑制され、炎症性サイトカインと細胞表面分子の合成が亢進する喘息は慢性炎症性気道疾患であり、炎症性サイトカインが極めて重要な役割を果たしている。
ジンクフィンガー結合タンパク質36(ZFP36)ファミリーには、ZFP36、ZFP36L1、ZFP36L2が含まれ、炎症を惹起することが報告されているRNA結合タンパク質(RBP)のひとつである。本研究では、喘息におけるZFP36ファミリーの役割を明らかにすることを目的とし、特に喘息における2型炎症のキープレイヤーであるTh2細胞とZFP36ファミリーの関係を明らかにした。
リアルタイムPCR解析により、ヒト白血球におけるZFP36ファミリーmRNAの優勢な発現が示された。GEOデータベースの公開データセットを用いた遺伝子発現解析では、喘息患者におけるZFP36ファミリーmRNAの発現が健常対照群と比較して有意に抑制されていた。ZFP36ファミリーsiRNAをTh2細胞にトランスフェクションすると、炎症性サイトカインIL-8、IFN-γ、CCL3/MIP-1α、CCL4/MIP-1β、TNF-α、細胞表面分子CCR4(CD194)およびPSGL-1(CD162)の発現が亢進した。IL-2、4、15を投与すると、Th2細胞によるZFP36ファミリーmRNAの発現は有意に抑制され、副腎皮質ステロイドは有意に増強した。
結論として、Th2細胞によって発現されるZFP36ファミリーは喘息患者において抑制されており、サイトカインや細胞表面分子の発現亢進につながった。喘息におけるZFP36発現の抑制は気道炎症の亢進に関与している可能性があり、ZFP36ファミリーは喘息を含む炎症性疾患の治療標的となりうる。
Relationship between serum IgA levels and low percentage forced expiratory volume in the first second in asthma.
J Asthma. 2024;61:1042-9
Imoto S, Suzukawa M, Takada K, Watanabe S, Isao A, Nagase T, Nagase H, Ohta K.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38376485/
(概要)
IgAは、喘息を含む呼吸器炎症性疾患において病原性を有することが示唆されています。血清IgA高値の喘息では、%FEV1が低値で、血清MIP-1βが高値であり、喘息病態とIgAとの関連が示唆されました。本研究は、NHOM喘息研究のデータを用いて、井本が筆頭著者として、東京病院の鈴川先生との共同研究で報告しました。
(Abstract)
喘息における血清IgA値とFEV1低値との関係
- 目的
- 免疫グロブリンA(IgA)は、喘息を含む呼吸器炎症性疾患において病原性を有することが示唆されている。我々は、血清IgAと喘息の臨床指標およびバイオマーカーとの関係を解析することを目的とした
- 方法
- 本研究は、NHOM喘息研究の事後解析である。本研究では、保存されている血清検体を用いて血清IgAを測定した。多変量線形回帰を用いて血清IgA値と臨床変数およびバイオマーカーとの関連を明らかにし、IgA高値喘息とIgA低値喘息との臨床指標の違いを分析した。
- 結果
- この研究では、572人の喘息患者が最終解析に含まれた。多変量線形回帰分析により、喘息患者の血清IgA値の高値と、強制呼気第1秒量(%FEV1)の低値、血清エオタキシン値の高値、血清ST2値の低値、血清MIP-1β値の高値は、独立して有意に関連していた(%FEV1、95%信頼区間[CI]、-8. 18--0.613、p<0.05;エオタキシン、95%CI、8.95-46.69、p<0.001;ST2、95%CI、-73.71--7.37、p<0.05;およびMIP-1β、95%CI、1.47-18.71、p<0.05)。さらに、IgA高値喘息(血清IgA 238mg/dL以上、n=270)とIgA低値喘息(血清IgA 238mg/dL未満、n=302)を別々に比較した。IgA高喘息では、%FEV1が有意に低く、アトピーの割合が高く、血清MIP-1β値が高かった。
- 結論
- 本研究は、血清IgAが、%FEV1や血清MIP-1βの上昇を介した炎症の亢進によって評価される喘息の転帰の悪化に関与している可能性を示唆している。
Changes in disease burden and treatment reality in patients with severe asthma.
Respir Investig. 2024;62:431-437.
Nagase H, Oka H, Uchimura H, Arita Y, Hirai T, Makita N, Tashiro N, Matsunaga K.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38492333/
(概要)
近年の喘息の増悪状況や治療薬の使用動向を保険データベースを用いて調査しました。別記の松永論文でも報告された、保険データベース研究のメインパートです。増悪は減少傾向であることが推定されましたが、まだまだ疾病負荷は残存していることを、長瀬が筆頭著者として報告しました。
(Abstract)
重症喘息患者における疾患負担と治療実態の変化
- 背景
- 生物学的製剤は重症喘息患者に臨床的に使用可能であるが、喘息コントロールの経時的変化は不明である。われわれは重症喘息患者における疾患負荷と治療の変化について検討した。
- 方法
- このレトロスペクティブ研究は、日本の健康保険データベース(Cross Fact)を使用し、2015年から2019年までの各暦年において、喘息と診断され吸入コルチコステロイド(ICS)による治療を継続した16歳以上の患者を対象とした。重症喘息は、高用量ICSに加えて1種類以上の喘息コントローラー薬を年間4回以上、経口コルチコステロイドを183日以上、または生物学的製剤を16週間以上使用したものと定義した。喘息増悪、処方、臨床検査の変化を調べた。
- 結果
- 人口統計学的特徴は研究全体を通して同様であった。喘息患者のうち重症喘息患者の数と割合は増加した(2015年2724人;15.3% vs 2019年4485人;19.0%)。喘息増悪が2回以上の重症喘息患者の割合は24.4%から21.5%に減少した。2015年と比較した各年の2回以上の喘息増悪のオッズ比(95%信頼区間)は、2016年が0.96(0.85-1.08)、2017年が0.86(0.76-0.97)であり、それ以降の年も有意な減少が認められた。喘息増悪に対する短時間作用型β作動薬と経口コルチコステロイドの処方は減少し、維持療法に対する長時間作用型ムスカリン拮抗薬と生物学的製剤の処方は増加した。
- 結論
- この研究では、重症喘息患者における疾患負荷と治療の改善が示された。喘息増悪を続ける患者の割合を考えると、重症喘息患者に対するアンメット・メディカル・ニーズが残っている。
共同研究論文
The efficacy and safety of Fluticasone Furoate/Umeclidinium/Vilanterol (FF/UMEC/VI) on cough symptoms in adult patients with asthma, A randomized double-blind, placebo-controlled, parallel group study: Chronic Cough in Asthma (COCOA) study.
J Asthma. 2025 Feb 3:1-11.
Tagaya E, Shinada J, Nagase H, Terada-Hirashima, J, Hojo M, Sugihar, N, Yagi O,Tsuji M, Akaba T, Masaki K, Fukunaga K, Ohbayashi H, Chiba K, Hozawa S, Atsuta R, Aoki Y, Hiranuma H, Gon Y, Tanaka A.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39874464/
(概要)
都内の複数施設を中心とした多施設共同研究で、喘息における持続性咳嗽に対する3剤併用療法の有効性と安全性を、ランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間多施設試験で検討しました。6週目の咳症状スコアやACQ-5スコアは、FF/UMEC/VI グループの方がプラセボよりも大きく減少しました。東京女子医科大学の多賀谷先生が筆頭著者としてまとめられ、当院は豊田の尽力のもと、長瀬が共同研究者として参画しました。
Advantage of spirometry over oscillometry to detect dupilumab's effect on small airway dysfunction.
Allergol Int. 2025 Jan 13:S1323.
Shirai T, Hirai K, Akamatsu T, Mizumura K, Sasano H, Harada N, Tanaka A, Sagara H, Masaki K, Fukunaga K, Kobayashi K, Nagase H, Miyahara N, Kanehiro A, Kitamura N, Sugihara N, Terada-Hirashima J, Hojo M, Chibana K, Tagaya E, Gon Y.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39809630/
(概要)
都内の大学病院を中心とした多施設共同研究で、デュピルマブ (IL-4受容体α抗体)に関する試験のサブ解析です。末梢気道機能不全(SAD)は喘息の重症度、コントロール、増悪と関連しています。オシロメトリーはSADを評価する信頼性の高い方法ですが、重症喘息における生物学的製剤のSADへの影響に関しては相反する知見が得られています。そこで、大規模な前向き研究でデュピルマブのSADに対する効果を評価しました。オシロメトリーでは、R5とR20は24週目に有意に改善しましたが、R5-R20、X5、Fres、AXは改善しませんでした。また、FVCおよび FEF25-75%で反映されるSADは患者全体で大幅に改善しましたが、X5およびAXは中枢気道および末梢気道機能不全 (LSAD, %FEV1<80%および%FEF25-75%<65%)を有する患者でのみ改善しました。これらの結果は、重症喘息におけるSADの検出において、オシロメトリーよりもスパイロメトリーの方が優れていることを示しています。結論として、スパイロメトリーは重症喘息患者全体におけるSADの改善を検出できるのに対し、オシロメトリーはデュピルマブ治療24週間後に肺機能障害のある特定の患者におけるSADの改善を検出できました。
オシロメトリーに関する豊富な知見を報告してきた静岡県立総合病院の白井敏博先生が筆頭著者として報告され、当院からは小林、長瀬が参画しました。
Practical Guidelines for Asthma Management (PGAM): Digest edition.
Respir Investig 63: 405-21, 2025 Mar 19.
Tamaoki J, Nagase H, Sano H, Kaneko T, Gon Y, Miyahara N, Sagara H, Tanaka A, Horiguchi T, Tagaya E, Akaba T, Tohda Y, PGAM committee in the Japan Asthma Society.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40112734/
(概要)
喘息管理に関する国際および国内ガイドラインは、一般的に呼吸器専門医向けに作成されています。そこで日本喘息学会は、多くの喘息症例を管理するプライマリケア医を対象として、喘息診療実践ガイドライン (PGAM)を作成しました。PGAMには、一般的な症状、誘因、診断基準、基本的な管理戦略、および頻繁に遭遇するtreatable traitsと併存疾患を概説した、理解しやすい表とリストが含まれており、本論文はそのダイジェストです。当院からは長瀬が参画しました。
Effectiveness of benralizumab in the Tokyo Asthma Study (TOAST): A real-world prospective interventional trial.
Allergol Int. 2024 Dec. 3.
Masaki K, Suzukawa M, Sasano H, Harada N, Miyazaki Y, Katsura H, Tagaya E, Terada J, Hojo M, Sugimoto N, Nagase H, Kono Y, Hiranuma H, Gon Y, Takemura R, Irie M, Nakamura R, Kabata H, Miyata J, Fukunaga K.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39632158/
(概要)
都内の大学病院を中心とした多施設共同研究で、重症喘息を対象とした生物学的製剤のリアルワールドで効果や効果予測因子を検討したシリーズのひとつです。ベンラリズマブ (IL-5受容体α抗体)による治療を受けた重症好酸球性喘息患者は、喘息コントロール、QOL、呼吸機能の大幅な改善を示し、OCSの使用量も減少しました。多変量解析により、ベースラインの血中好酸球数(400個/μl以上)と呼気一酸化窒素分画(22ppb以上)がベンラリズマブに対する治療効果の独立した予測因子であることが同定されました。慶應義塾大学の正木先生を筆頭著者とし、当院からは杉本、長瀬が共同研究者として参加しました。
Predicting dupilumab effectiveness with Type-2 biomarkers: A real-world study of severe asthma.
Allergol Int. 2025 Jan;74:144-155.
Mizumura K, Gon Y, Harada N, Yamada S, Fukuda A, Ozoe R, Maruoka S, Abe S, Takahashi K, Tanaka A, Sagara H, Akamatsu T, Shirai T, Masaki K, Fukunaga K, Kobayashi K, Nagase H, Miyahara N, Kanehiro A, Kitamura N, Sugihara N, Kumasawa F, Terada-Hirashima J, Hojo M, Chibana K, Tagaya E.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39277433/
(概要)
都内の大学病院を中心とした多施設共同研究で、重症喘息を対象とした生物学的製剤のリアルワールドで効果や効果予測因子を検討したシリーズのひとつです。重症喘息において、血中好酸球数やFeNOなどの2型バイオマーカーは、デュピルマブ (IL-4受容体α抗体)によるFEV1や喀痰症状改善の予測因子として有用なことを、real-worldで示しました。日本大学 水村先生を筆頭著者として、当院からは小林、長瀬が共同研究者として参加しました。
Real-world incidence of and risk factors for abemaciclib-induced interstitial lung disease in Japan: a nested case-control study of abemaciclib-induced interstitial lung disease (NOSIDE).
Breast Cancer. 2025 Jan;32:177-185.
Nakayama S, Yoshizawa A, Tsurutani J, Yoshimura K, Aoki G, Iwamoto T, Nagase H, Sugimoto N, Kobayashi K, Izumi S, Kato T, Miyazaki Y, Kurihara Y, Taira N, Aihara T, Kikawa Y, Mukai H.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39556171/
(概要)
乳がん治療薬である、アベマシクリブの重篤な副作用である間質性肺疾患(ILD)の正確な発生率とリスク因子は、実臨床では不明であり、日本の進行乳癌患者におけるアベマシクリブ誘発性ILDの発生率とリスク因子が検討されました。アベマシクリブ服用患者において、アベマシクリブ誘発性ILDの発症率は5.0%(n=59/1189)、死亡率は0.7%(n=8)でした。ILDの発症時期は治療開始後180日以内に発症することが最も多く(64.4%)、アベマシクリブ誘発性ILDの発症率は、ECOG PS≧2または過去の間質性肺炎(IP)の病歴と有意に関連していました。本研究では、日本におけるアベマシクリブ誘発性ILDの実世界での発生率とリスク因子を初めて明らかにしました。
本研究は乳がん専門医との共同研究による成果であり、呼吸器内科医がILDのタイプ、重症度、因果関係を中央判定しました。長瀬が中央判定委員会を構築し、小林と杉本は画像判定チームに加わりました。
Management of severe asthma during the COVID-19 pandemic: A retrospective study using a Japanese database.
Allergol Int. 2024 Oct 23:S1323-8930.
Matsunaga K, Oka H, Uchimura H, Arita Y, Hirai T, Makita N, Nagase H.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39448325/
(概要)
保険データベースを用いた研究で、COVID-19蔓延期間中の喘息増悪が減少した可能性を、山口大学の松永先生を筆頭著者とし、長瀬が参画した共同研究で報告しました。
Pioneering a paradigm shift in asthma management: remission as a treatment goal.
Lancet Respir Med. 2024;12:96-99.
Lommatzsch M, Buhl R, Canonica GW, Ribas CD, Nagase H, Brusselle GG, Jackson DJ, Pavord ID, Korn S, Milger K, Taube C, Virchow JC.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38071999/
(概要)
海外の研究者との共著で、喘息の臨床的寛解の考え方と、各国の定義をレビューしました。長瀬から日本の定義についても言及されています。